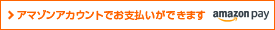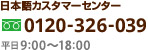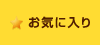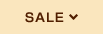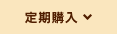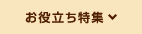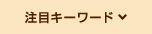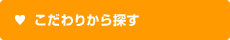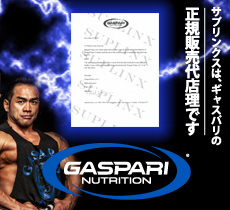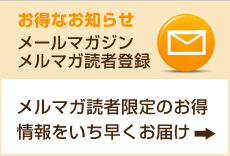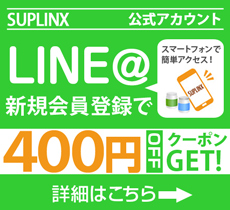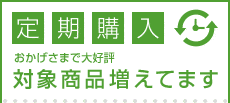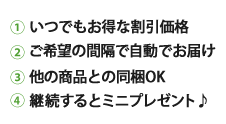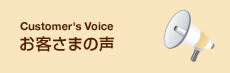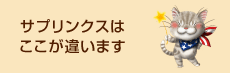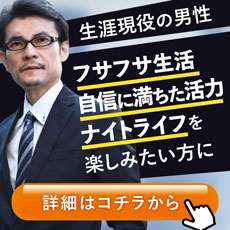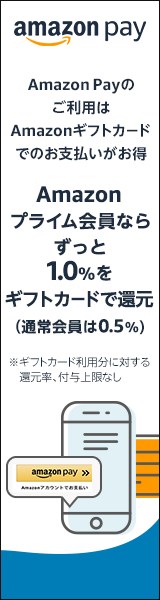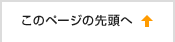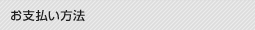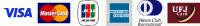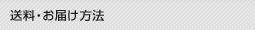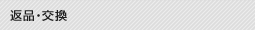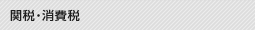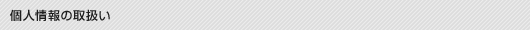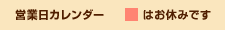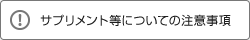亜鉛サプリメントの飲むタイミングと効果的な摂取方法

亜鉛は私たちの健康維持に欠かせない必須ミネラルとして知られています。一方で、食事だけでは十分に摂取できないケースもあるため、サプリメントを活用する人が増えています。そこで今回は、亜鉛サプリメントの基本的な知識から効果的な飲むタイミングや摂取方法、注意点までを整理してご紹介します。
亜鉛を上手に取り入れることで、免疫力や肌、薄毛や抜け毛、男性の健康など幅広い面でサポートが期待できます。毎日の栄養バランスを考慮しつつ、不足しがちな成分はサプリメントで上手に補うことがポイントです。ぜひ日々の生活習慣に活かし、健康的な毎日を過ごすための参考にしてください。
亜鉛サプリメントについて

そもそも亜鉛とはどのような栄養素で、サプリメントを利用する意義は何でしょうか。基本的な知識を押さえ、サプリメントのメリットや活用シーンを理解しましょう。
亜鉛は数多くの酵素反応に関わり、私たちの身体にとって重要な役割を果たしています。味覚や免疫システム、皮膚や髪の健康など、多岐にわたる機能を正常に保つために欠かせません。食事だけで不足しやすい要因として、現代人のライフスタイルや偏りがちな食生活が挙げられます。
そのため、必要量を確保するのが難しい場合には、効率的に亜鉛を補えるサプリメントの活用が有効です。市販の亜鉛サプリメントには、亜鉛以外にも健康サポート成分が配合されていることが多く、総合的に栄養を補いたい方にも選ばれています。
毎日の食事に組み合わせてサプリメントを適切に利用すれば、不規則な食習慣をカバーしつつ健康面でのリスクを軽減できます。ただし、あくまでサプリメントは補助的な位置づけですので、できるだけ普段の食生活を見直すことが基本となります。
亜鉛が含まれる食べ物

食事から摂取できる亜鉛の多い食材は多岐にわたります。普段の食事で亜鉛を補いやすくする工夫や、さまざまな食事パターンのポイントを確認してみましょう。
亜鉛は動物性食品や魚介類に多く含まれており、比較的吸収率も高いとされています。一方、ナッツや豆類などの植物性食品にも豊富に含まれるため、ベジタリアンの方でも工夫次第で亜鉛不足を防ぐことができます。
ここでは代表的な亜鉛源と、それらを食事に取り入れる際のポイントを整理してみましょう。ビタミンCやクエン酸の有無によって亜鉛の吸収率は左右されますので、一緒に摂る食材や飲み物にも目を向けるとより効果的です。
動物性食品
牛肉や豚肉、レバーなどの動物性食品は亜鉛含有量が多く、人体への吸収効率も高いことが特徴です。特に赤身の肉やレバーは亜鉛量が豊富で、必要な分をしっかり補給しやすい食材として知られています。
ただし、過剰な動物性脂肪の摂取は健康リスクにつながる可能性があるため、バランスを取りながら適度に取り入れることが望ましいです。調理方法や部位選びなどで脂質を抑えながら、亜鉛を効率よく摂取する工夫をすると良いでしょう。
魚介類
魚介類の中でも特に有名なのが牡蠣の亜鉛含有量です。牡蠣は豊富なミネラルを含む食材として重宝されており、亜鉛の補給源としてもトップクラスの評価を受けています。
イワシやカツオなども亜鉛を比較的多く含むため、魚料理を日常的に取り入れることで健康維持に役立ちます。加えて和食中心の方には特に食べやすい食材が多いため、味付けや調理法の工夫で飽きずに続けることができます。
植物性食品
ナッツ類(カシューナッツ、アーモンドなど)や豆類(大豆、レンズ豆など)は、動物性食品を控えたい方でも取り入れやすい亜鉛供給源です。特にきなこといった大豆製品は日常食品として利用されており、手軽に亜鉛を取り入れることができます。
ただし、植物性食品に含まれるフィチン酸が亜鉛の吸収を阻害する場合があるため、発酵食品やビタミンCを含む食材と一緒に摂るなど、組み合わせを工夫することで吸収を高められます。
野菜と果物
野菜や果物自体の亜鉛含有量は、動物性食品や魚介類に比べると少なめです。とはいえ、ビタミンやミネラルを総合的に摂取する上では欠かせないため、バランスの良い食習慣を保つうえで重要な存在です。
特にビタミンCを豊富に含む野菜や果物は、亜鉛の吸収率をサポートします。例えばレモンやパプリカなどを食事に加えることで、サプリメントや他の亜鉛源から摂取した亜鉛の利用効率を高める効果が期待できます。
食事での工夫
亜鉛を効率よく吸収するには、ビタミンCやクエン酸などを同時に摂取すると良いと言われています。例えば果物や酢の物などを一緒に食べたり、柑橘系のドレッシングをサラダに使うなどの工夫が挙げられます。
また、調理段階でフィチン酸を減らすために豆類をしっかりと水に浸す、発酵食品を取り入れるなどの対策も有効です。調理やメニューの工夫によって亜鉛を最大限活かせる食事を心がければ、サプリメントとの併用効果もさらに高まります。
亜鉛の健康への重要性

亜鉛が不足するとどのような影響が出るのか、また健康を守る上でなぜ必要不可欠なのかを詳しく見ていきます。
亜鉛は免疫機能を維持する上で欠かせず、不足すると風邪や感染症にかかりやすくなるリスクが高まるとされています。さらに味覚障害や脱毛、肌荒れなど、身体のさまざまな部分に不調が現れやすくなることも報告されています。
特に成長期の子どもや妊娠中の女性、そして忙しく栄養バランスが崩れがちな現代人にとっては、亜鉛を意識して摂取することが大切です。必要量を満たすことで代謝や細胞分裂を円滑にし、日々の健康をより充実させる効果が期待できます。
亜鉛の効果的な摂取方法

サプリメントだけでなく、毎日の食事や他の栄養素との組み合わせで効率よく亜鉛を取り入れる方法を整理します。
まずは、亜鉛を多く含む食品を意識的に食事に組み込みましょう。肉や魚、ナッツ類などさまざまな種類の食材をバランスよく摂取することで、複数の栄養素を同時に補うことができます。
サプリメントを取り入れる場合は、ビタミンCやクエン酸など吸収を促進する成分と同時に摂るのがおすすめです。また、マグネシウムや鉄など、ほかのミネラルとのバランスにも気を配ることで、より効率的な栄養摂取が実現します。
亜鉛サプリメントの種類と選び方

市販されている亜鉛サプリにはさまざまな形状や配合成分があります。特徴を理解し、自分に合った製品を選択しましょう。
亜鉛サプリメントはタブレットやカプセル、パウダーなどさまざまな形状で販売されています。携帯性や飲みやすさ、味の好みによって選択肢を狭めるのも一つの方法です。
また、亜鉛以外にビタミン類や他のミネラルが配合されている複合サプリメントも多く見られます。一度に複数の栄養素を補えるメリットがある反面、個々の配合量をきちんと把握し、過剰摂取を避けるよう注意しましょう。
亜鉛不足の症状

亜鉛が不足すると味覚異常や脱毛など、身体に様々なサインが現れることがあります。その具体例を挙げ、予防策を考えます。
亜鉛不足が続くと味が分かりにくくなる味覚異常や爪が割れやすくなるなど、さまざまな不調が表面化することがあります。男性の場合は性機能への影響が出ることも報告されており、日常生活に支障をきたすケースもあるため注意が必要です。
こうした症状を防ぐためには、まずは食生活を見直して亜鉛含有量の多い食品を取り入れたり、必要に応じてサプリメントを活用することが大切です。早期に対処することで重度の不足リスクを下げ、健康トラブルを少なく保つことにつなげられます。
亜鉛サプリメントと免疫力の関係

免疫力を保つために欠かせない亜鉛。サプリメントで足りない分を補うことで期待できる効果や注意点を解説します。
免疫細胞の活性化や抗酸化作用といった幅広い役割を担う亜鉛は、体内の防御機能を維持するために不可欠です。亜鉛が不足していると、外部からの細菌やウイルスに対抗する力が弱まり、病気にかかりやすくなる可能性があります。
サプリメントで補給する際には、適切な摂取量を守ることに加え、生活習慣全体を見直すことが重要です。十分な睡眠やこまめな運動と併用しながら亜鉛を補給することで、免疫力を含めた総合的な健康管理に役立てられます。
亜鉛サプリメントと肌の健康

肌荒れやニキビなど、肌トラブルと亜鉛には深い関わりがあります。サプリメントでの摂取のメリットを知り、スキンケアに生かしましょう。
亜鉛は肌の新陳代謝を促進し、ターンオーバーを整える働きを持つため、肌荒れやニキビの改善に寄与すると考えられています。特に思春期や大人ニキビに悩む方にとって、適量の亜鉛摂取は一つのアプローチとなるでしょう。
ビタミンAやビタミンCなどの補助栄養素と組み合わせることで、より高い相乗効果が期待できます。ただし、過剰摂取はかえって悪影響を及ぼす可能性があるため、用法用量を守りながら取り入れることが大切です。
亜鉛サプリメントと男性の健康

男性特有の健康悩みにも亜鉛は深く関与しています。そのためサプリメントの利用が一つの選択肢として注目されています。
亜鉛は男性ホルモンの生成や精子形成に関係するとされ、男性特有の健康維持に欠かせない存在です。不足すると活力や体力の低下を感じやすくなる場合もあり、意識的な摂取が求められます。
食事からの摂取が充分でないと感じる場合には、サプリメントを活用するのも効率的です。ただし、個人差がありますので、特定の悩みがある方は医師や栄養士に相談しながら適切な摂取量を見極めるようにしましょう。
亜鉛サプリメントの副作用と注意点

サプリメントの過剰摂取や他の薬との飲み合わせには注意が必要です。安全に続けるためのポイントを押さえましょう。
亜鉛を過剰に摂取すると吐き気や下痢、めまいなどの症状が起きるケースがあります。また、亜鉛の過剰摂取が鉄や銅など他のミネラルの吸収を阻害する可能性も指摘されています。
ほかの薬を服用している方は、相互作用を避けるためにも必ず医師または薬剤師に相談しましょう。まずはサプリメントのパッケージに記載された推奨量を守り、サプリと食事とのバランスを考慮しながら継続することが大切です。
まとめ

亜鉛サプリメントの基本や各種メリット、注意点などを振り返り、日々の健康維持への応用方法を再確認します。
亜鉛はその重要性が高いにもかかわらず、現代人の食生活では不足しがちな栄養素の一つです。食材選びや調理法の工夫などでできるだけ自然な形で補給しつつ、必要があればサプリメントを上手に取り入れることがポイントになります。
過剰摂取や相互作用に配慮しながら継続していけば、免疫力から肌、男性の健康まで幅広い恩恵を得られる可能性があります。まずは適正な摂取量とタイミングを意識し、より健やかな毎日を目指しましょう。
執筆:日本ニュートリション協会認定サプリメントアドバイザー 村田ゆり
|
亜鉛サプリメントはこちらから ぜひ参考にしてみてください! |