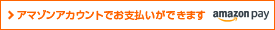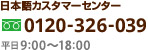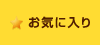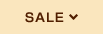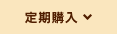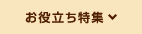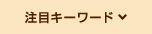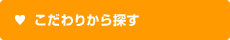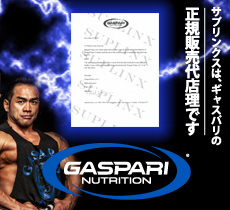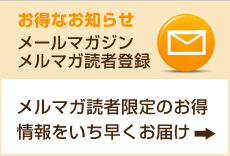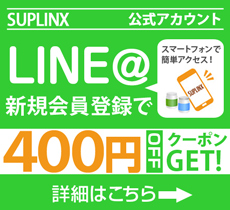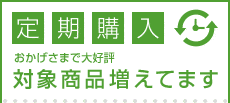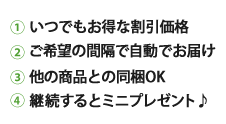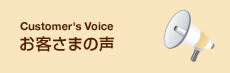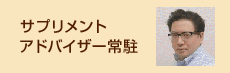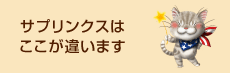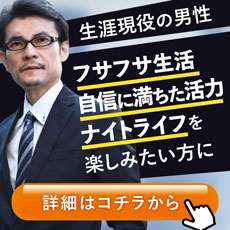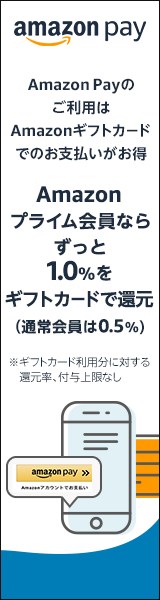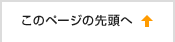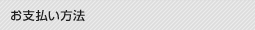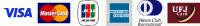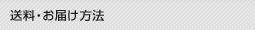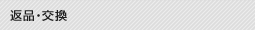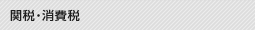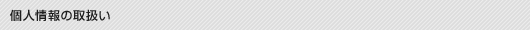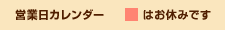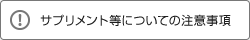夏の冷え性(隠れ冷え)を徹底解説!原因・症状・対策を網羅

日本の夏は高温多湿である反面、屋内外の温度差や冷たい飲食物の摂取などにより、意外にも体が冷えやすくなります。特に、冷えに弱い方は気温の高さを感じていても末端や内臓が冷え、夏バテだけでなくさまざまな不調を招きかねません。そこで、本記事では夏に多く見られる隠れ冷えの実態やその対策を詳しくご紹介します。
夏の冷え性は冬の冷え性とは異なり、気づかないうちに進行しやすいのが特徴です。この記事では、夏の冷え性を引き起こす具体的な原因や症状、そして体を温めるための実践的なケア方法を丁寧に解説します。毎日を快適に過ごすためのヒントを得て、冷え知らずの健康的な夏を目指しましょう。
夏の冷え性(冷え症)とは?

一般的に冷え性といえば冬のイメージが強いですが、実は暑い季節にも体温調節がうまくいかず、手足やお腹周りが冷えることがあります。これは、外の気温が高いにもかかわらず、冷たい飲食物や強い冷房の影響を受けて内臓が冷えきってしまうために起こる現象です。こうした夏ならではの隠れ冷えが続くと、自律神経が乱れやすくなり、だるさや食欲不振などの体調不良につながることがあるため注意が必要です。
夏に体が冷えやすい主な原因

夏は気温が高いにもかかわらず、現代では冷房の効いた室内で長時間過ごすことが多くなっています。そのほか、冷たい飲み物やアイスなどの摂取が増えることで、内臓を冷やしやすくなり、血行不良や代謝の低下を引き起こす場合もあります。さらに、暑さを避けて活動量が減ると筋肉量が落ちてしまい、体温を生産しにくい状態になることも冷え性の原因の一つです。
冷房の効き過ぎによる自律神経の乱れ
真夏の屋内外の温度差が大きいと、体は一瞬で冷気にさらされてしまいます。その結果、体温を一定に保とうとする自律神経が過度に働き、バランスを崩しがちです。特にオフィスや商業施設では冷房が強く効いていることが多く、長時間いるだけで末端冷えや疲労感を感じやすくなるため、注意が必要です。
冷たい飲食物の摂り過ぎ
暑い季節はどうしてもアイスクリームや冷たい飲み物に手が伸びがちですが、これらを大量に摂取すると内臓が冷えて血行が妨げられやすくなります。内臓冷えは消化機能や代謝の低下につながり、夏バテや慢性的な疲労を引き起こす原因にもなります。食事での冷たい麺類、冷やしドリンクの過剰摂取に気をつけ、温かいスープや常温に近い飲み物を時々挟むことが大切です。
室内外の温度差が与える影響
夏の外気温は高いものの、室内に入ると一気に冷える温度差が生じるため、体への負担は大きくなります。急激な気温変化に体が追いつけず自律神経が乱れると、血流が不安定になり冷えが進行しやすいです。さらに、外で汗をかいている状態で涼しい室内に移動すると、皮膚表面が冷え、余計に体全体が冷えやすくなるケースも増えています。
筋肉量不足・運動不足
筋肉は体の熱をつくり出す大切な器官であり、夏場も適度な運動を続けていないと筋肉量は減少してしまいます。運動不足が続くと基礎代謝が下がり、体温を保つためのエネルギーを十分に生産できなくなることも冷え性を進行させる原因です。エアコンのある快適な環境でじっとしているだけでは体温維持が難しいので、軽いストレッチやウォーキングなどを取り入れて、筋肉量をキープしておきましょう。
夏の冷え性が引き起こす症状と不調

冷房の効いた室内と外の暑さを行き来するうちに、体温管理が難しくなって疲れを感じる人も多いでしょう。こうした冷え性由来の不調は、一時的なものにとどまらず、慢性的な不調に発展しかねません。以下のような症状は見逃さず、早めに対策を講じることが大切です。
こ手足の冷えとむくみ
夏でも指先や足先が冷たいと感じる場合、血液循環が悪化しているサインです。めぐりが滞ることで水分をうまく排出できず、むくみを伴うケースも少なくありません。特に女性は、薄着やサンダルなどで足首が冷えやすいため、ちょっとした保温対策を取り入れるだけでも症状の緩和が期待できます。
だるさ・疲労感が抜けない
体温が低下するとエネルギー産生も落ちてしまい、日中の活動量が少なくても疲れやすくなります。さらに、自律神経の乱れが原因で熟睡しづらくなり、朝起きてもだるさが残るという悪循環に陥りがちです。夏バテと勘違いしやすい症状ですが、冷えからきている可能性もあるため、身体を温めることを意識してみると良いでしょう。
胃腸の不調や食欲不振
内臓が冷え込むと胃腸が正常に働きにくくなり、食欲がわかない、もしくは食べても不調を感じやすくなります。慢性的に冷たいものを摂りすぎると、腸内環境が乱れて栄養をうまく吸収できない悪影響にもつながるでしょう。夏こそ温かい食事や常温の飲み物を取り入れて、内臓機能をいたわる必要があります。
体の中からケア!食事で行う夏の冷え対策

夏場はどうしてもさっぱりした冷たいものばかりに手が伸びがちですが、体温を保つには温かい食事や飲み物が欠かせません。ここでは、食材の選び方や食事の取り入れ方など、体の内側から冷えを改善するポイントをまとめています。
身体を温める食材と献立のコツ
ショウガやネギ、黒ゴマなどの薬味や、根菜やかぼちゃなどの「陽」に分類される食材は、体を温める効果が期待できます。これらを積極的に取り入れた献立を考えることで、夏でも内臓冷えを和らげ、代謝を高めることができます。たとえば、ショウガ入りの炒め物や具だくさんの味噌汁などを日常的に取り入れると、食事からのアプローチだけでも大きな効果が得られます。
温かいスープ・飲み物習慣を取り入れる
朝食に温かいスープを加えるだけで、体の中心から温まる感覚を実感できるでしょう。コーヒーやお茶を飲む時も、なるべくホットで摂取することで内臓を冷やしにくくなります。食事の合間や夜寝る前にも温かいハーブティーなどを取り入れることで、冷えの進行を抑え、より快適に過ごしやすくなります。
漢方薬・サプリメントの活用
個人の体質や症状に合わせて漢方薬やサプリメントを利用することも、夏の冷え対策では有効な方法の一つです。特に血行を促進するタイプの漢方や、ショウガ成分を多く含むサプリメントは、冷えを感じやすい方に重宝されています。ただし、自己判断で始める前に専門家に相談し、自分の体に合った製品を選ぶことが大切です。
体の外からケア!衣類・生活習慣・運動での対策

いくら食事で体を温めても、衣類や生活習慣が不適切だと対策効果が半減してしまいます。夏でも必要に応じて暖房を使ったり、体を冷やさない工夫を重ね着や入浴方法で行うことで、内側と外側の両面から冷えを緩和できます。ここでは、具体的にどのようなことに気をつければ良いかを説明していきます。
エアコンと上手に付き合うポイント
冷房の設定温度は27〜28度程度を目安にし、直接風が当たらないようにすることが基本です。サーキュレーターや扇風機を併用して空気を循環させると、寒さを感じにくい快適な室内環境を作れます。温度設定だけでなく、室内の湿度管理も重要なので、湿度を適度に保つよう心がけましょう。
ツボ押し・足浴・半身浴の効果
足裏やふくらはぎなど、血行を促進するツボを軽く押すことで肌表面だけでなく内臓の温度も上げやすくなります。さらに、足浴は短時間でも下半身を温める効果が高く、全身のめぐりを改善する手軽な方法です。ぬるめのお湯にゆっくり浸かる半身浴も合わせて行うと、リラックス効果と冷え対策を同時に実感できます。
適度な運動とストレッチの取り入れ方
屋外では暑さを理由に運動を控えがちですが、室内でのヨガや軽い筋トレ、ストレッチなどは続けやすい運動です。こまめに体を動かすと筋肉量をキープできるため、基礎代謝が上がり冷えにくい体質へ変わりやすくなります。特にデスクワークが多い方は、休憩時間に立ち上がって軽く体をほぐすなど、小さな動きを積み重ねましょう。
重ね着・衣類選びの注意点
涼しげなファッションが主流の夏ですが、冷えが気になる人は薄手のカーディガンやストールなど、すぐに羽織れるものを用意しておきましょう。通気性と保温性を両立させる機能性インナーも活用すると、屋内外の温度差を上手に乗り切ることができます。靴下やレッグウォーマーなど、足首を冷やさないアイテムも意外なほど重宝します。
放置は禁物!夏の冷えのリスクと注意点

冷えを軽く考えてしまうと、知らず知らずのうちに体調不良が深刻化することもあります。特に女性にとってはホルモンバランスの乱れや免疫力の低下などを引き起こし、長期的な影響が及ぶこともあるため要注意です。
女性特有の不調が長引く可能性
冷えによって血流が滞ると、女性特有の悩みである生理痛やPMSの悪化を招くことがあります。さらに、ホルモン分泌が乱れることにつながり、生理不順や気分の浮き沈みが激しくなるケースも見られます。こうした不調が長引くと日常生活に大きな支障をきたすため、早めの対策が求められます。
免疫力低下や慢性的な体調不良
体温が下がると免疫細胞の働きが鈍くなり、病原菌やウイルスへの抵抗力が落ちると考えられています。その結果、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなり、回復にも時間がかかる場合があります。夏の冷えが慢性化すると、季節の変わり目や冬場にも不調を引きずり、体調管理が難しくなるので注意が必要です。
冬とは違う!夏の冷え性対策ならではのコツ

冬の冷え性とは異なり、夏の冷えは冷房や冷たい食事による影響が大きいため、対策方法も少し違ってきます。特に、就寝時のエアコン設定や寝具の使い方など、季節性を考慮した工夫が重要です。これらの対策を取り入れることで、夏の夜を快適かつ健康的に過ごせるようになるでしょう。
暖房と冷房のバランスが重要
気温が高い夏でも、冷えが強いと感じる場合は、短時間だけ暖房を併用する選択肢も視野に入れると良いでしょう。冷房で下がった体温を一時的に戻すことで、自律神経の過度な乱れを緩和できるケースがあります。部屋全体を暖めるほどではなくても、必要なときにピンポイントで温度調整できるように工夫しておくと安心です。
寝冷えを防ぐための工夫
真夏でも寝ている間に体が冷えすぎると、朝起きたときの疲労感や頭痛につながることがあります。エアコンが直接体に当たらないよう風向きを調整したり、薄手の掛け布団や腹巻を活用してお腹を冷やさないようにすることが大切です。特に夜は代謝が落ちる時間帯なので、寝冷え対策を徹底しておくことで冷え性による体調不良を予防できます。
まとめ:夏ならではの冷え性対策を意識し、健康的な毎日を

夏の冷え性は、冷房、冷たい飲食物、運動不足などさまざまな要因が重なり合って引き起こされます。冬のようにわかりやすい冷えとは異なり、気づかないうちに体が冷えてしまうことが多いので、早めのケアが肝心です。体を温める食事や適度な運動、衣類の工夫などを総合的に取り入れ、おだやかで元気な夏の日々を送りましょう。
執筆:日本ニュートリション協会サプリメントアドバイザー 村田ゆり
|
栄養バランスのサポートにマルチビタミン&ミネラル! ぜひ参考にしてみてください! |