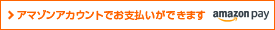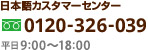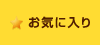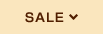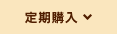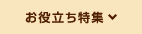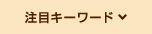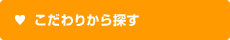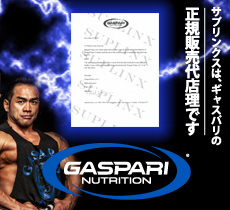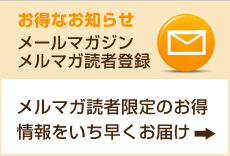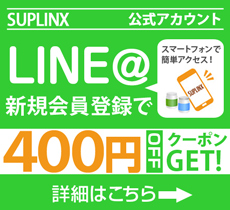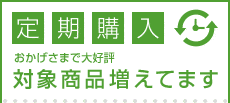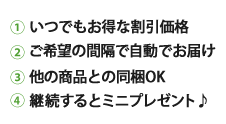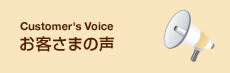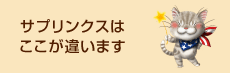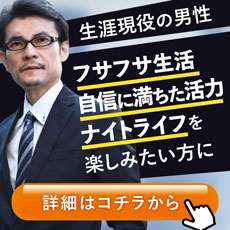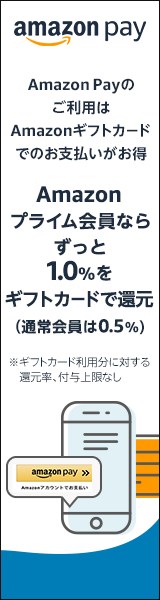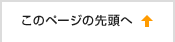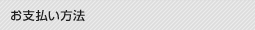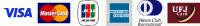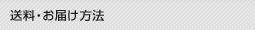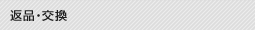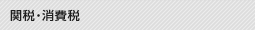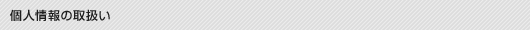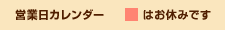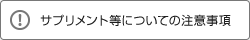筋肥大を徹底解説!筋力向上・筋持久力との違いからトレーニング・食事法まで

筋肉を大きくする“筋肥大”を実現するには、単に重いものを持ち上げるだけではなく、正しいトレーニングプランと栄養管理、そして十分な休養が欠かせません。本記事では、筋肥大の基礎概念や筋力向上・筋持久力との違い、さらに効率的に筋肉を増やすためのポイントを徹底的に解説します。
初心者から上級者まで、目的別に具体的なトレーニング例や食事の組み方、注意点を網羅し、筋肥大を着実に目指すために大切な情報をまとめました。
筋肥大とは?筋力向上・筋持久力との違い

最初に、筋肥大の定義や筋力向上・筋持久力との違いを理解することで、目標を明確にし、適切なアプローチを取ることができます。
筋肥大とは、筋繊維がトレーニングによる刺激で微細に損傷し、修復の過程で太くなる現象を指します。筋繊維のサイズが増大することで、見た目の変化だけでなく基礎代謝の向上も期待できます。加えて、エネルギー消費量が高まり太りにくい体質へ近づける利点も挙げられます。
筋肥大の定義と目指すメリット
筋肥大とは、筋繊維がトレーニングや栄養摂取によって太くなる現象を指します。見た目の変化としては、引き締まった体や明確に分かる筋肉のラインが得られる点が大きなメリットです。さらに、筋肉量が増えることで、日常生活での身体的パフォーマンスが改善し、基礎代謝向上によるダイエット効果も期待できます。
筋力向上との違い
筋力向上は、重い負荷を持ち上げる力を高めることを中心に置きます。これは単に筋肉量を増やすだけでなく、中枢神経の適応や筋繊維の動員率の向上も深く関係しています。筋肥大を目指すトレーニングと筋力向上を重視したトレーニングには共通部分もあれば負荷設定や回数設定の違いもあるため、目的に応じたプログラムを組むことが望ましいでしょう。
筋持久力と筋肥大の関連性
筋持久力向上を目的とする場合は、比較的低負荷で高回数をこなすトレーニングが重視されます。その際でも筋肉はある程度の太さを持つことで、持続的な力発揮をサポートすることが可能です。ただし、筋肥大を最大化する場合には、やや高負荷の刺激も必要となるため、目的とするパフォーマンスに合わせて負荷と回数を調整することが鍵となります。
筋肥大のメカニズムと成長原理

筋肉が太くなる過程とホルモン、栄養の働きを理解してこそ、効果的なトレーニングや食事計画が立てられます。
筋肥大は、トレーニングによる微細な筋損傷と、修復過程で生じる超回復の組み合わせによって実現します。トレーニングで筋繊維に負荷がかかると、筋細胞がダメージを受けますが、身体はその損傷を修復し、さらに強化することで筋肉の太さが増すのです。これを繰り返していくと、少しずつ筋繊維は厚みを増していきます。
成長ホルモンやテストステロンなどのホルモンは、筋肉の修復と成長を助ける重要な存在です。高負荷トレーニングや適切な栄養摂取でこれらのホルモンの分泌が促進されると、より効率的な筋肥大が期待できます。
筋繊維が太くなる仕組み
筋繊維は、小さな傷を修復する過程で以前より強く太くなるという特性を持ちます。これを“超回復”と呼びますが、休養と十分な栄養がなければこのプロセスは円滑に進みません。加えて、同じ負荷を繰り返すだけでは筋肉が刺激に慣れてしまうため、少しずつ重量や回数を増やすことも必要な要素となります。
ホルモン分泌と栄養摂取の関係
筋肥大には成長ホルモンやテストステロンなどのホルモンが深く関わっています。高負荷トレーニングや適度な休養、質の高い睡眠はこれらホルモンの分泌を高める大きな要因です。また、トレーニング直後にタンパク質や炭水化物をバランスよく摂取することで、ホルモンの効果を最大限に活かし、筋肉の修復と成長をサポートできます。
筋肥大に効果的な基本トレーニングの原則

筋肉を太くするために押さえておきたい基本的なトレーニングの考え方を解説します。
筋肥大では、適切な負荷と回数、そして十分な休息がカギとなります。特に高重量で短時間に強い刺激を与える方法は、“張り”刺激を与えやすく、筋肥大を効果的に促進します。フォームを安定させることも重要で、狙った筋肉にしっかりと効かせるためには、正しい姿勢とゆっくりとした動作を意識しましょう。
また、動作をコントロールする“スロートレーニング”を取り入れると、筋肉を休ませる時間を短くしつつ、継続的に負荷を与えやすくなります。インターバルの長さは、トレーニングの目的によって調整する必要がありますが、あまり長い休息を取らないことで成長ホルモンをより多く分泌させる方法も存在します。
高重量・低回数トレーニングのメリット
高重量・低回数トレーニングは、筋肉に大きな張力を与えることで、効率的に筋肥大を誘発しやすいのが特徴です。少ない回数で限界に近い負荷を扱うため、一度のセットで強い刺激を与えられます。この手法は筋肉の断面積拡大を狙ううえで、大きな効果を期待できます。
スロートレーニングとインターバル調整
スロートレーニングとは、挙上や降ろす動作をゆっくり行い、常に筋肉が緊張状態にある時間を長くする方法です。短時間で最大限の刺激を与えたい場合は、インターバルを短めに設定することで成長ホルモンの分泌も促進しやすくなります。逆に、筋力向上やフォームの安定を狙う際には、適度にインターバルを取って疲労を回復させるのが効果的です。
長期的・計画的に負荷を増やすポイント
筋肥大を目指すには、トレーニング計画のなかでプログレッシブオーバーロードを意識することが重要となります。重量や回数を段階的に上げることで、常に新たな刺激を筋肉に与えられます。これにより慣れを防ぎ、持続的な成長を見込むことが可能です。
負荷・回数・セット数・頻度の最適な設定方法

トレーニングプランを実践する上で重要な、負荷や回数などの設定を具体的に見ていきます。
筋肥大を効果的に狙うには、適切な負荷と回数設定によって筋肉を追い込む必要があります。よく使われるのがRM法で、自分が最大何回持ち上げられる重さ(〇RM)を目安に負荷を設定します。例えば8〜12回で限界を感じる重さは、筋肥大を目指す上で多くのトレーニングプログラムにおいて推奨される範囲といえます。
加えて、セット数やインターバルの長さも筋肥大に大きく影響する要素です。筋肉をより肥大させたい場合は、セット数を多めにして、インターバルを60〜90秒程度にするなどの工夫を行います。一方、筋力向上を重視するならば、長めに休息をとり、より高重量を扱えるように調整します。
セット数・インターバルは目的別に調整
筋肥大を主目的とする場合は、各種目で3〜4セット程度、休息時間をやや短めに取って筋肉が疲労しきるように設定することが多いです。筋力向上を図りたいときには、より少ない回数ながら重めの負荷を扱うためにインターバルを十分に確保し、各セットを高いパフォーマンスで実施できるようにします。
週のトレーニング頻度と分割法の考え方
週に何回トレーニングを行い、どの部位を重点的に鍛えるかは筋肥大の成果を左右する要素です。全身法では1回のセッションで全身をまんべんなく刺激できる反面、疲労が溜まりやすい場合があります。一方、分割法は部位を曜日ごとに分けて集中的に鍛えられるため、疲労管理がしやすいのがメリットです。自身のスケジュールに合わせて柔軟に選ぶことが大切です。
筋肥大を加速させる食事と栄養戦略

筋肉をつけるには質の高いトレーニングだけでなく、栄養面でのサポートも欠かせません。
筋肥大を目指す際には、エネルギーバランスをプラスにしつつも、良質な栄養素をしっかりと摂ることが重要です。タンパク質は筋肉合成の基盤であり、炭水化物はトレーニングに必要なエネルギーを供給します。脂質はホルモン分泌を支える役割があるため、極端に避けずに適量を守りながら摂取しましょう。
食事だけでは必要量を満たすのが難しい場合、プロテインやアミノ酸などのサプリメントを取り入れると補助的に効果を得やすくなります。
タンパク質・炭水化物・脂質のバランス
筋肥大では1日の総摂取カロリーのうち、タンパク質の割合をしっかり確保しながらも炭水化物と脂質をバランス良く摂ることが鍵となります。筋肉はエネルギー不足だと十分に成長できないため、炭水化物を制限しすぎるとトレーニングの質が落ちる可能性もあります。理想的な栄養バランスを模索しつつ、カロリーの過不足を管理することが大切です。
プロテイン・アミノ酸・サプリメントの活用
食事だけで必要なタンパク質を摂るのが難しい場合、プロテインや必須アミノ酸をサプリメントとして採り入れることは非常に有効です。特に運動直後は筋肉合成が高まりやすいため、そのタイミングで摂取すると効果的です。
効率を高める応用トレーニングとテクニック

より高い効果を目指すために、技術的に工夫したトレーニング方法やモチベーション管理術を紹介します。
基本的なトレーニングを続けるだけでも筋肥大は見込めますが、特定のテクニックを駆使することでさらに効率を高めることができます。たとえば、ドロップセットやスーパーセットなどを取り入れると、短時間で強い締めくくりの刺激を与えられ、マンネリ化を防ぎながら筋肉に新鮮な負荷を与えられます。
ドロップセット・スーパーセットの導入
ドロップセットは、1セットの最終レップで限界に達したらすぐに重量を軽くし、連続でさらに数レップ行う方法です。スーパーセットは、互いに拮抗する筋肉の種目などを休まずに連続実施する方法を指します。いずれも短時間での高密度な刺激を得る手段として有効で、筋肉の“追い込み”を強化したい場面で活躍します。
トレーニング記録&モチベーション管理の重要性
トレーニングを継続的に行ううえで、記録を残すことは非常に大切です。前回との比較ができるため、負荷を微調整しやすくなり、目に見えて成果を感じられればモチベーションも維持しやすくなります。少しずつでも以前の自分を上回ることを目標にして、トレーニングの質と継続性を高めましょう。
ジムと自宅トレーニングを使い分けるコツ
ジムは各種マシンやフリーウェイトを使って多角的に筋肉へ刺激を与えられますが、忙しいときや移動時間が取れないときには自宅トレーニングも有効です。腕立て伏せやスクワット、チューブやダンベルなどを活用することで、十分に筋肉へ刺激を与えることができます。両方を状況に応じて使い分けることで、トレーニングを習慣化しやすくなり、筋肥大のペースを落とさずに済むでしょう。
まとめ:効率よく筋肥大を目指すために

最適なトレーニングと栄養、そして休養をしっかりと行うことで、筋肉を着実に成長させることが可能です。全体のポイントを整理して出発点を固めてください。
筋肥大を効率的に進めるためには、まず筋みがきの基礎概念を理解し、適切な負荷設定やフォームを押さえることが大切です。筋力向上や筋持久力との違いを把握しながら、自分に合った目標やプログラムを組むことで、迷いなく取り組めるでしょう。
関連記事
執筆:臨床栄養協会認定サプリメントアドバイザー 長谷川貴志
|
スポーツニュートリション系サプリメントはこちらから ぜひ参考にしてください! |